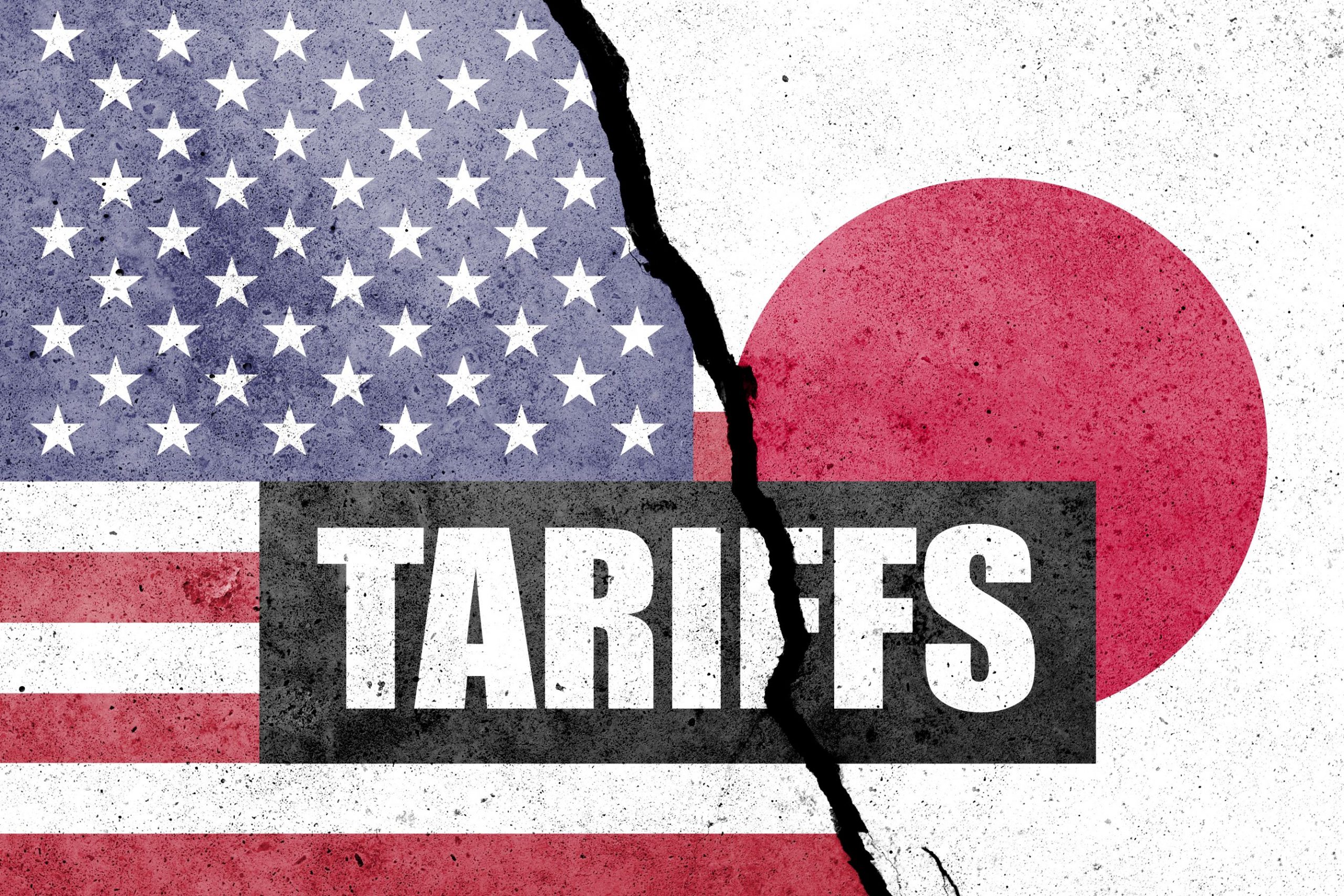![]() グローバル
グローバル
グローバル
グローバル
国際税務は経済戦争?!(5)
租税法律主義の裏側
前回のコラムで国際税務の基本的な原則である「PE(Permanent Establishment)無ければ課税なし」について説明した。再度エッセンスだけを凝縮すると、他国の居住法人は、ある国にビジネス上の拠点を持たなければ、原則としてその国で課税されないという原則である(詳細については前回のコラム国際税務は経済戦争?!(4)をご覧ください。)。
PE無ければ課税なしという原則は、もとはといえば国際間の課税権の調整から生じてきた考え方である。その背景の一つに租税法律主義がある。租税法律主義は以前のコラム(国際税務は経済戦争?!(3))でも簡単に触れているが、要はある国が税金を課すには、議会の承認を経た法律(税法)に基づかなくてはならないという考え方である。例えば日本においては、日本国憲法第84条に「あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする」と規定されている。このような法規範は、国民の人権保護という観点からは基本的には望ましい考え方であるが、その反面議会さえ通ってしまえば、どのような課税でも行えるという側面がある。
ボストン茶会事件
現在主要各国は自国の個人や法人のみならず、外国の個人や法人にも一定の課税を行っている。例えば日本では、法人税関連法規で「内国法人は」と規定されている場合通常課税の対象は日本法人だけであるが、さりげなく単に「法人は」と規定されている場合は、日本法人だけでなく外国法人も課税対象となっていることが多い。これは、日本法人と同じような活動を行っている外国法人がある中で、日本法人にだけ課税をして外国法人に課税しないと日本法人だけが不利な競争条件でビジネスを行わざるをえないからであるというような説明が行われることがある。ただし、外国法人に対する課税がこのようなコンセプトに基づいて常に行われているという保証はなく、日本国に痛みが発生しない外国法人への課税範囲はどうしても何の規制もなければ拡大していく方向性になる。これは各国みな同じである。
このような形で外国法人の課税範囲がどんどん広がってくると、外国法人側としては自らの国が議会に代表を出しているわけではない外国政府によって一方的に課税されるという状況に反発し国際間の緊張状態が生まれることになる。古い話にはなるが象徴的な出来事はボストン茶会事件である。アメリカから議員が選出されていないイギリス議会で成立した法律によりお茶に重税がかけられ暴動に発展した事件で、後のアメリカ独立戦争への流れを作った歴史上の重要イベントである。「代表無くして課税なし」というスローガンは有名であるが、現在の外国法人も何も対策を打たなければ似たような状況になっていてもおかしくない。
PE無ければ課税なしという考え方による国際調整
PE無ければ課税なしの考え方は、要は外国法人への課税の歯止めをかけるために生まれてきたコンセプトである。約100年前に制定された国際連盟モデル租税条約によって国際的なフレームワークとして確立したものとされている。外国法人に対する課税をどこで線引きするのか難しい中で、他の国に物理的な事業拠点を築かなければ、ビジネスの発展性も限られるはずだというある種の割り切りのもとで、エスカレートする課税合戦を抑止する効果を狙ったものであるといえる。この考え方は、それなりの納得感をもって各国に受け入れられ、その後1977年に制定されたOECDモデル条約に引き継がれて国際的に定着していくことになる。
デジタル経済の発展と従来の国際課税のフレームワークの崩壊
この長きにわたって定着してきたPE課税に対する考え方の問題点がデジタル経済の発展と共に露呈することになった。今日のデジタルエコノミーの定着により、GAFAのようにPE課税がそのよりどころとしていた各国への物理的な拠点を必要とせず、各国から巨額の売上をあげることが可能となったためである。また、デジタルテクノロジーに関連する無形資産の高付加価値化にともない、大きな設備投資がなくても世界中のいろいろな場所に高度なデジタル拠点を作ることができるようになったことも旧来のフレームワークに風穴をあけることとなる。これまでのオールドエコノミーでは、海外からの投資の誘致には、投資に適した市場環境やロジスティック面でのインフラ、十分な教育水準を有する労働力や経済力を伴う人口に基づく購買力などが無いと難しかったが、デジタル産業の誘致はこれよりはるかに低いハードルで行えるようになったのである。
国際間の税率引き下げ競争
このようにIT企業の海外進出が容易になると、特に海外投資を受け入れるバックグラウンドが十分でない国が魅力的な税制を提供することで自国経済を活性化しようとする流れが生まれてきた。これに対抗する形でいわゆるG7諸国のような十分な経済力を有する国々もこれに追随し、国際的な税率引き下げ競争に発展していったのである。日本の法人税率も実効税率ベースで2000年には40%を超えていたのが、2018年には29.74%にまで低下した。この間所得税率は最高約37%から45%に上昇し、消費税は5%から8%(2019年には10%)に上昇していることから、日本が国際的な法人税率引き下げ競争にいかに影響を受けていたかがわかる。
このような流れに対して対抗策として登場したのがBEPSである。次回はBEPSによる各種対抗策とその後の動向について触れていくこととしたい。
飯村 鉄雄(Iimura Tetsuo) / NAC顧問(香港常駐)及びグループ国際税務室長
デロイトトーマツ税理士法人東京事務所ビジネスタックスサービス(マネージングダイレクター)、PwC税理士法人東京事務所(パートナー)、大手損害保険会社国際税務リーダー等を経てNAC顧問就任。東京大学法学部卒、日本国公認会計士有資格者。