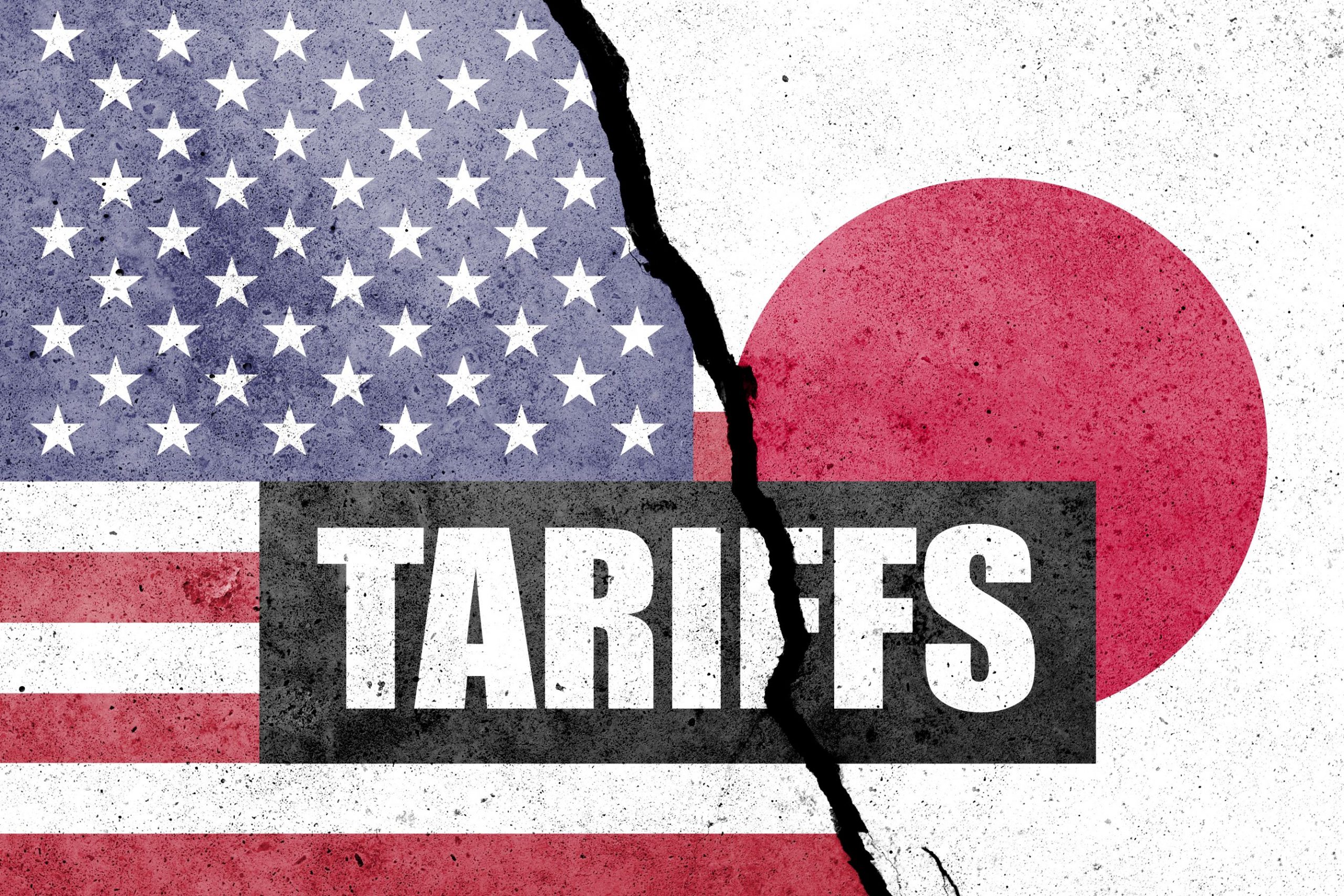![]() グローバル
グローバル
グローバル
グローバル
国際税務は経済戦争?!(4)
PE無ければ課税なし
国際税務に少しでも関心がある方であれば、「PE無ければ課税なし」という言葉を聞いたことがある方は結構いらっしゃるのではないかと思う。国際税務でPEといえばPermanent Establishmentの略。日本語では恒久的施設と訳されている。一般には耳慣れない言葉だが、簡単に言うと海外にあるビジネス上の拠点のことである。これは法人にのみ適用される概念ではなく、個人にも適用されるので注意が必要だ。
海外にあるビジネス上の拠点というとすぐ思い浮かぶのは海外の子会社であろう。ただ、海外子会社は原則として日本の親会社のPEにはならない。海外子会社は日本の親会社とは別法人だからだ。典型的なPEは日本法人の外国支店である。駐在員事務所は収益活動への関与が無ければ通常PEにはならない。
それでは外国支店さえなければPEが無いと言えるのかといえばそうではない。たとえば日本法人の商品のセールスマンが外国のホテルに滞在して、その国で商品の販売契約を取り付けているようなケースでは、そのホテルがPEと認定されることがある。法的な位置づけや登記とは関係なく、純粋にその国で商売の拠点となっているかどうかが問題なのである。それでは販売担当の社員が海外に出張すればPEになるのかというとそれはそうでもない。恒久的施設という言葉の通り通常一定期間の長期的滞在が必要となるからだ。
PEの有無による課税上のインパクトとリスク
このようにPEの有無により課税がオールオアナッシングで決定されるので、PEの有無は極めて重要である。どのように課税されるかは各国の税制と租税条約によるが、おおまかにいうとその国で得られた利益の内PEに帰属する利益というのを算定して、それにその国の法人税率をかけた税額を海外親会社に申告して納付させるというのが標準的な課税方法である。ただ、ビジネスに関係しているかどうか、長期的かどうか、対象の物理的な施設が固定的施設かどうか、PEに帰属する利益は何か、あたりの要素に主観が入り込むため、海外の税務当局との間で重要な論争になりやすい。租税条約のカバーがある場合は、ある程度フレームワークは規定されているが、それでも主観的な判断による食い違いは避けられない。
アメリカのPE問題
たとえばアメリカのケースを例に挙げてみよう。多くの日本企業がアメリカに子会社を保有している。そして通常日本から駐在員が派遣されていて、主としてアメリカ子会社の管理活動に従事している。ここで、この駐在員が、もっぱらアメリカの子会社の管理活動のみに従事していれば、多くの場合PEの問題は生じない。ただ、しばしばこのような駐在員は親会社の特定のビジネス部門に所属していて、親会社にも同時に籍を置き親会社の名刺も持っていて、親会社の商品の販売促進を手掛けていたりする。このような場合、あくまでもリスクがあるかないかというレベルの話ではあるものの、事実関係によってはそのような駐在員が在籍する海外子会社が日本の親会社のPEとして認定される可能性がないとは言い切れない(だから海外子会社は原則として日本の親会社のPEにならないとさっき説明したのである。)。
アメリカの場合特に注意を要する点がある。アメリカは無申告の場合時効はない。したがって、アメリカに進出して20年以上たつという企業も少なくないと思うが、もし20年前から続けているビジネススタイルが今になってPEと認定されたと仮にしたら、20年分の課税所得に不納付期間に比例して課されるペナルティと利息(利息は基本複利計算)で想像もできない多額の納税額になったりしかねない。
このような事態を避けるためにわざと所得ゼロの申告書(アメリカではprotective returnという。)を期限内に提出し、時効の時計を進めるとともに無申告という状態を避けるというやり方もある。ただし、PEがあるという認識がないのに、わざわざ当社はアメリカにPEがあるかもしれませんと宣告するような申告書を出すことは心理的には抵抗があるということは容易に想像できる。このようにPEの問題は解決しようとしてもそう簡単ではないのである。
アメリカはなぜこのような過酷とも思える税制を外国法人に強いるのか。理由は明確で、もしいやならアメリカという市場から出ていけばいいだけではないかと割り切っているからである。経済的に恵まれない国々のように、海外からの投資によって自国経済を支えなければならないような国はこのような税制はとれない。よって富める国はますます富み、そうでない国はますます苦しくなるという構図が国際税務の世界でもいたるところで展開しているのである。
次回はこのようなPE課税体系が経済の実体に適合しなくなってきたため生じた変化についてふれることにしたい。BEPSの一連の動きに関係するムーブメントについてである。
飯村 鉄雄(Iimura Tetsuo) / NAC顧問(香港常駐)及びグループ国際税務室長
デロイトトーマツ税理士法人東京事務所ビジネスタックスサービス(マネージングダイレクター)、PwC税理士法人東京事務所(パートナー)、大手損害保険会社国際税務リーダー等を経てNAC顧問就任。東京大学法学部卒、日本国公認会計士有資格者。