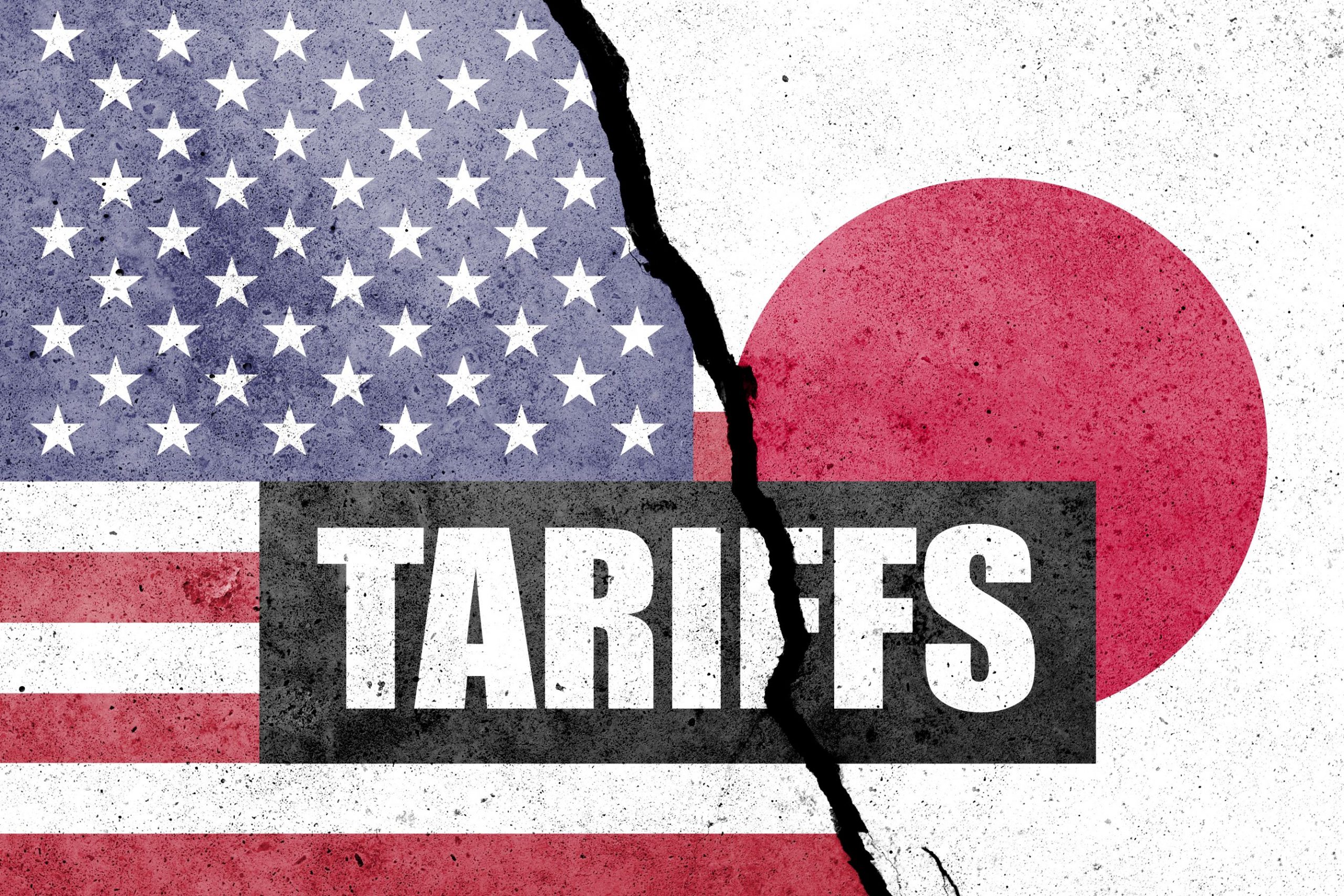![]() グローバル
グローバル
グローバル
グローバル
国際税務は経済戦争?!(3)
租税法律主義
租税法律主義という言葉をご存じだろうか。これよりも有名なのは罪刑法定主義でご存じの方も多いはずだ。そう、どのような行為が犯罪になるかはあらかじめ法律で定められていなければならないという考え方である。これがないと国民は何が許されているかわからず、突然身体の自由を拘束される事態となり日常生活が成り立たなくなる。
同様に租税法律主義とは、何にどのような形で税金を課すかはあらかじめ法律で定められていなければならないという考え方である。これがないと、どんな経済活動にどのような税金がどの程度課されるかについての予測ができず、経済活動が成り立たなくなる。さらに、法律の成立には国民の代表からなる議会を通さなければならないので、政府による一方的な課税をけん制するという効果も見込めることになる。
国際税務における租税法律主義の限界
海外でも租税法律主義の考え方を採用している国がほとんどである。しかし国際税務のフィールドでは、この租税法律主義がうまく機能しない。なぜなら日本の法律の効力は、原則として日本国外には及ばないからである。ただそうだからといって外国法人への課税を全くあきらめてしまうわけにもいかない。税収減という側面のみならず日本企業が国際競争で不利な立場に立たされかねないからだ。このため、少なくとも他国と同レベルの課税は行いたいと考えるのが自然である。
外国法人への源泉徴収
この点の解決方法の一つとして、外国法人への源泉徴収がある。源泉徴収とは、配当や利子、ロイヤリティ等の支払いの際に源泉税相当額を差し引いて外国法人に支払い、控除した源泉税を支払者が国税に納付する義務を負うという制度である。ポイントは外国法人には日本法の効力は及ばないが、支払者である日本法人には及ぶという点にある。
源泉徴収の問題点
源泉徴収の問題点は、必要以上に税額が大きくなりがちという点だ。源泉税は経費を控除しないグロスの収入にかかるものであるため、同じ税率でも法人税よりはるかに税負担は重くなる。例えば、アメリカの連邦法人税率は21%であるが、源泉税の一般的な税率は30%になっている。このままでは、逆に外国法人に過大な税金を課すという結果になり、経済活動に影響が出かねない。
租税条約の登場
これらの諸問題を解決するために登場したのが租税条約である。租税条約の構想は第二次世界大戦前からあり、1928年には国際連盟によるモデル条約が制定されている。戦後1963年にOECDモデル条約が制定され、日本の締結する租税条約はこのOECDモデル条約がベースとなっている。
租税条約の目的は、国際課税の基本的なフレームワークや二重課税や租税回避に関する対処法を提示することによって、二国間の健全な投資・経済交流に資することであるとされる。このうちOECDモデル条約に規定されている源泉税の軽減税率は、先述の過剰な源泉税の課税を回避して経済交流を促進するためのものであることがわかる。
日本の租税条約締結の歴史
日本は1954年の日米租税条約の締結を皮切りに1960年代から1970年代前半にかけてスウェーデン、(西)ドイツ、デンマーク、イギリス、オランダ、スイス、フランスなどの西欧諸国と相次いで租税条約を締結している。このころの日本は独立を回復し、欧米の資本や技術を導入して高度経済成長による経済先進国入りをようやく達成した頃である。このため、日本から外国への投資よりも圧倒的に外国から日本への投資が多く、配当、利子、ロイヤルティいずれも受取より支払が多かった。もうおわかりであろう。欧米との租税条約の締結によって、日本の源泉税が大量に欧米に流出していったのである。
その後、1980年代には日本の経済力がさらに強くなり、プラザ合意による円高などの影響でアジア諸国への海外進出が盛んに行われていたのはご存じのとおりである。このころこれらのアジア諸国と日本との間で相次いで租税条約が締結されている。あれ、これはどこかで見たことがある図式ではないか。カールマルクスの名言ではないが歴史は繰り返すのである。
飯村 鉄雄(Iimura Tetsuo) / NAC顧問(香港常駐)及びグループ国際税務室長
デロイトトーマツ税理士法人東京事務所ビジネスタックスサービス(マネージングダイレクター)、PwC税理士法人東京事務所(パートナー)、大手損害保険会社国際税務リーダー等を経てNAC顧問就任。東京大学法学部卒、日本国公認会計士有資格者。