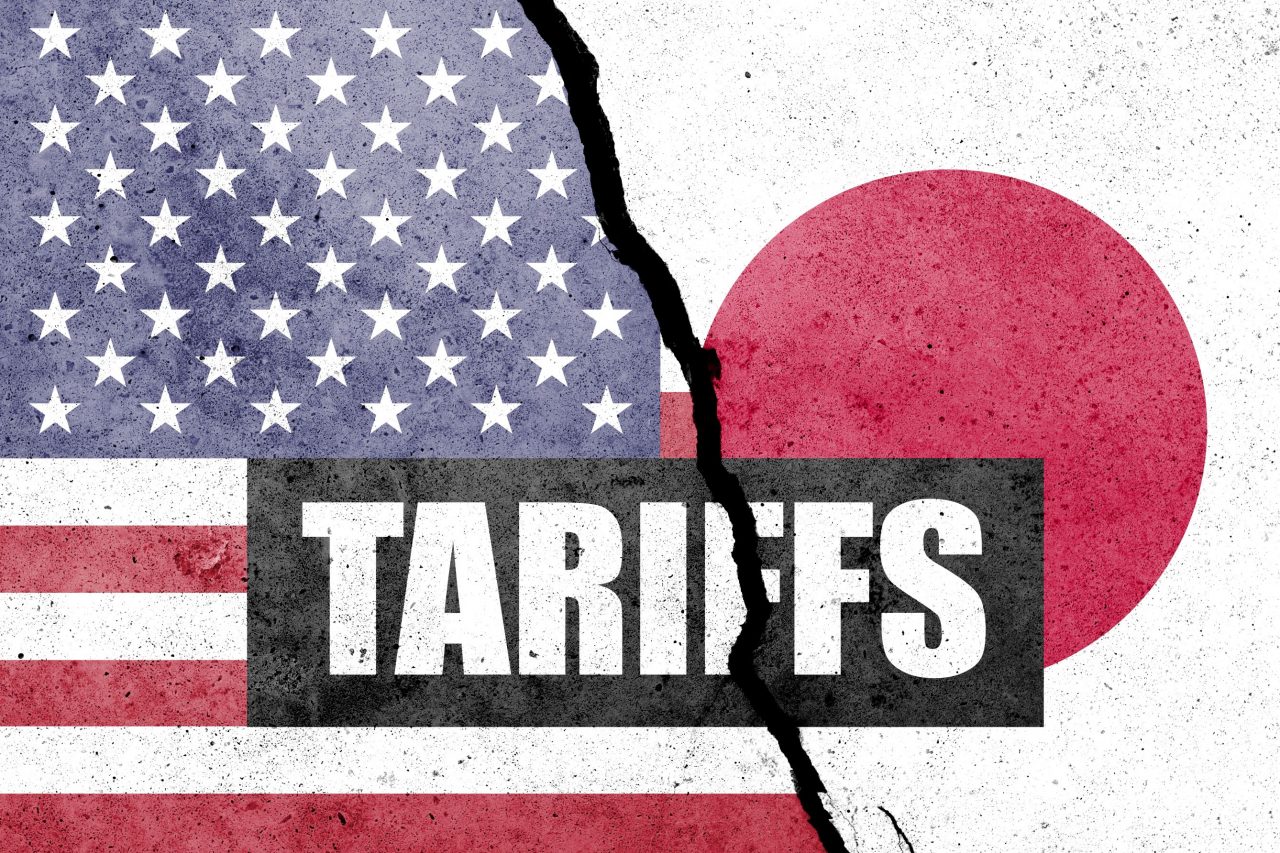不透明なトランプ関税
いちおう幸いなことにというべきなのか、トランプ関税の率が15%に決まり最悪の事態は避けられた感がある。ただし、この15%が上限なのかそれとも既存の関税率に上乗せなのか、また自動車の関税がいつから15%に引き下げられるのかなど不透明感は払拭されていない。現状EUと異なる取り扱いとなっているところも微妙である。
このような状況を見るにつけ、ある程度以上の年齢の方は1980年代の日米貿易摩擦を思いだされるのではないだろうか。そう、あの日本車をハンマーでたたき壊すやつである。日本の自動車産業にとっては、北原白秋作詞の唱歌ではないが、「この道はいつか来た道」なのである。
15%というとピンとこないかもしれないが、消費税10%の重さを知るわれわれ日本人には容易に実感できる。よって15%の上乗せのマーケットに与える影響は重大であるといっても過言ではない。
トランプ関税の転嫁の方法と移転価格税制
この15%を転嫁する方法は、シンプルに考えて理論上①販売価格に上乗せする②米国販売子会社に負担させる③製造元の日本の親会社が負担する、のざっくり3通りである。
このうち①の販売価格に上乗せする方法はマーケットシェアへの影響もさることながら、米国消費者への関税の影響を最小限にしたいトランプ大統領を刺激することにもなりかねない。したがって、ここでは①の方法はとれないと仮定する。
次に②の米国販売子会社に負担させる方法であるが、この方法によると15%の関税分だけ米国販売子会社の利益が削られることになる。その結果米国販売子会社のモチベーションがダウンするだけでなく、米国販売子会社の採算がとれずビジネスモデルが崩壊する危険性がある。その上さらに待ち受けているのが移転価格税制である。
昨今の移転価格税制は、輸出価格が市場価格(=第三者価格)であるということを立証することよりは、TNMM(取引単位営業利益法)にみられるように、海外子会社の利益率が適正であることが重要な要素となっている。すなわち、米国子会社の利益が十分でないということは、米国子会社への販売価格が適正でないからだという推論的判断により、よって適正な市場価格はもっと低いはずだと米国税務当局が認定してくる傾向にある。この結果米国子会社の利益(=課税所得)が移転価格税制の適用によって増加することになり、米国で実際に儲かってもいない架空の利益について追加課税が生じるのである。トランプ関税の結果としてさらに移転価格税制が発動されれば、まさに踏んだり蹴ったりである。このシナリオは避けたいであろう。
アンチ・ダンピング課税
それでは③製造元の日本の親会社が負担する方法はどうか。①や②よりもましなようであるが、問題が無いわけではない。まずは移転価格税制を発動するのはアメリカだけではないということである。日本の税務当局もなぜ関税の影響を全部日本が負わなければならないのかという点に着目する可能性は十分にある。ただし、実際問題としては、日本の税務当局がこのような状況下で移転価格税制を発動する可能性は低いとみている。なぜなら国税もしばしば政治の風向きを読むからである。
それよりもこわいのは、アメリカのアンチ・ダンピング課税である。アンチ・ダンピング課税とは、輸出国の国内価格よりも低い価格の輸出について課税するもので、アメリカ固有のものではない。WTOの前身のGATTによって世界的に認められており、日本による発動事例もある。このアンチ・ダンピング課税において比較対象となる日本国内における販売価格に関しても、複雑な原価計算や商品及び販売ルートの多様化、為替レートの変動など検討すべき点は多く、客観性が確保される保証はない。
このように、今後の日本の輸出企業は、トランプ関税だけでなく、前門の虎、後門の狼ならぬ、「前門の移転価格税制、後門のアンチ・ダンピング課税」に対処した上で、ビジネスにおいて適正利潤を上げ続けるという多元連立方程式を解かなければならないのである。
飯村 鉄雄(Iimura Tetsuo) / NAC顧問(香港常駐)及びグループ国際税務室長
デロイトトーマツ税理士法人東京事務所ビジネスタックスサービス(マネージングダイレクター)、PwC税理士法人東京事務所(パートナー)、大手損害保険会社国際税務リーダー等を経てNAC顧問就任。東京大学法学部卒、日本国公認会計士有資格者。